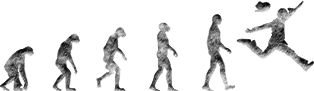「王さんから奪三振記録を奪う!」江夏が実現させた恐るべき有言実行

伝説のサウスポー
日本プロ野球史上最高の投手は誰か?という問いに、必ず名前が挙がるのが江夏豊だ。若い頃は先発完投型の左腕速球投手として活躍し、晩年は技巧派のリリーフ投手として華麗なる変身を遂げた。
そんな江夏が持つ最高の記録といえば、1シーズン401奪三振という空前絶後の記録だ。この記録はメジャーリーグ(MLB)でも類を見ない大記録である(MLB記録はノーラン・ライアンが持つ383奪三振)。この記録を達成したのは高卒2年目、即ち弱冠20歳の時のことだから、凄いサウスポーだったことがわかる。実は、この奪三振記録達成にも壮大なドラマがあったのだ。
俺はこっち、お前はあっち
江夏は1966年のオフ、野球では無名の大阪学院高校から阪神タイガースにドラフト1位で入団した。高校時代の江夏は速球一本槍で、変化球は全く放れなかったのである。なんとかカーブを覚えて、新人の年は12勝をマーク。今で言うと阪神の後輩である藤浪晋太郎のようなものだが、藤浪は多彩な変化球を持っているのに対し、当時の江夏は速球以外では中途半端なカーブだけ。つまり、ほとんどストレートばかりの高卒新人が2桁勝利を挙げたのだ。江夏のポテンシャルが伺い知れる。
当時、阪神のエースは右腕の村山実だった。村山は読売ジャイアンツとの試合前、次期エースの江夏にこう言った。「俺はこっち、お前はあっち」と。
「こっち」と指差した先には、試合前の打撃練習をしている長嶋茂雄の姿があった。村山と長嶋といえば、天覧試合で村山が長嶋にサヨナラホームランを打たれて以来、宿命のライバルと言われていた。つまり村山は江夏に、俺と長嶋さんとの勝負を邪魔するな、と言ったのだ。
「あっち」の指先にいたのは王貞治だった。長嶋と共にON砲というコンビを組み、この頃には一本足打法を完成させてホームランの量産態勢に入っていた。村山は江夏に対し、お前は王をライバルとせよ、と指令したのである。
予告奪三振
2年目の68年、江夏は凄いペースで勝利と奪三振を積み重ねていった。この頃は完全にマスターしたカーブでも三振を取れるようになったのである。村山を上回る江夏の活躍により、阪神は巨人と激しい首位攻防戦を行っていた。当時の巨人はV9時代の始まりで、既に3連覇を果たしていた。
シーズン終盤の9月17日、阪神甲子園球場ではまさしく天下分け目の天王山を迎えていた。阪神が2ゲーム差で首位巨人を追う直接対決の4連戦である。18日はダブルヘッダーだったので、3日間で4連戦という日程だった。
初戦、阪神は絶好調の江夏を先発に立てた。実はこの時、優勝争いだけではなく、大きな記録がかかっていた。稲尾和久が持つ1シーズン353奪三振まであと8個と迫っていたのである。江夏は試合前「王さんから新記録を奪う」と宣言した。
江夏は序盤から快調に飛ばし、三振の山を築いた。迎える打者は王。江夏は見事に三振を奪い新記録達成!と思った。
ところが江夏の計算違いで、王から奪った三振は353個目であり、即ちタイ記録だったのだ。新記録は王さんから奪うと宣言した以上、それを実行しなければならない。
ここから江夏は、次の王に回るまでの8人の打者に対して、三振を取らないで打ち取るという投球術を披露した。三振を取らないと言っても首位攻防戦で、しかも0-0という試合展開だったから打たれるわけにもいかない。中でも困ったのが、投手の高橋一三に対して2ストライクに追い込んでしまったことだ。投手から新記録なんてケッタクソ悪い。江夏はド真ん中にそっと投げて、なんとかセカンドゴロに打ち取った。
三振を取ることもなく打者が一巡して、再び王との対戦を迎えた。江夏の投球ぶりを見て、王はハッキリと自覚していた。江夏は本気で俺から新記録を奪う気だ、と。
江夏は王に対し、たちまち1ボール2ストライクと追い込んだ。王は逃げも隠れもせず、フルスイングしてきている。この偉大な打者に対し、江夏はド真ん中に剛速球を投げ込んだ。ホームランボールである。
王は待ってましたとばかりに全力でこのボールを叩きにいった。ところが、ド真ん中のはずの球は唸りを上げて浮き上がり、王のバットの遥か上を通過した。空振り三振で新記録達成!マウンド上の江夏は飛び上がって喜び、ベンチでも村山が拳を振り上げていた。
この試合にはまだ続きがあって、両軍ともに点が取れず0-0のまま延長12回に突入した。その裏、江夏はサヨナラヒットを放ち、新記録に花を添えた。しかも、中1日を経て第4戦にも江夏は先発、見事に完封勝利を挙げたのだ。
このシーズン、江夏の奪三振記録は401個まで伸びたが、この記録は二度と破られることはないだろう。首位攻防戦での予告奪三振といい、延長12回完封後の中1日登板完封といい、現在の野球では考えられないことだが、当時はこんな侍がいたのだ。