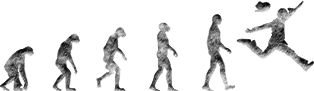〈愛〉のとらえ方。大人の男はこれを〈かなしい〉と読め

日本語には豊かな味わいというものがあります。例えば「愛」という漢字は「いとしい」とも「かなしい」とも読みます。なぜ「愛」が「かなしい」なのか、そこを考えて自分の愛情観を深いものにしましょう。
愛は祈りでもある
思えば母が子供を産むときは、自分の楽しみや幸せも念頭にはあるでしょうが、むしろ生まれてくる子供に対する思いのほうが次第に強くなっていくようです。ついには、場合によってはたとえわが身を犠牲にしてでも、我が子の幸せを優先したいという「祈り」のような心境にも近づいていきます。それが母性というものの不思議さ、素晴らしさであると言われています。
男にはちょっと分かりづらいかもしれませんが、でもカマキリのオスは、繁殖行為の後ですぐにメスに命を提供してその身を「餌」にしてしまうそうですから、父性の中にも愛の「かなしさ」というものはたっぷり含まれているととらえることはできます。
命の継承はかなしいもの
そもそも人を「愛する」ということは、単に好きになるというのとは違って、相手の運命にかかわりを持とうと願うことなのです。相手の幸せづくりに自分も参加しようとする意志のことです。
ところが人の運命というものは、個人の意志や力を超えた「天」に委ねられたものでもあります。それゆえに、人間の側から見れば、運命はしばしば不本意で「かなしい」ものになってしまいます。海から遡上したサケも、子を産んですぐ死んでいきますが、命のバトンタッチというものはそのように、ある種の悲哀を伴わずにはいないものなのです。
愛別離苦の定め
師弟愛も同様です。男女の愛も同様です。出会いと別れがあり、運命が非情にもそれらを切り分けてしまいます。運命のはからいの奥には、全ての喜怒哀楽を貫いて人の瞼を熱くする玄妙な「かなしさ」が横たわっています。それと向き合うとき、人はしみじみとした命への沈潜を知るのです。
愛する者との別れの辛さを〈愛別離苦〉と呼びますが、愛の賛歌のあとにはそれが待っているということを知るのも、大人になるということの一面ではないでしょうか。
悲母観音の姿
生命というものの本質は、ある種の積極性です。個体維持も種族保存も、積極性の形だと言えます。しかしそれを単なる「肯定」や「楽観」と理解するだけでは、日本人的な受け止め方であるとは言えませんね。
「悲母観音(慈母観音)」をご存知ですか。あのしっとりとした姿の中に、日本人の生命感が宿っています。幼子を抱いた観音像。幸せの表情ですが、どことなく寂しい姿でもあり、そこに日本の母の理想がうかがえる気がします。人は我を忘れて子を思い、妻を思い、親を思い、国を思うとき、かなしいものなのです。
念願が悲願になるまで
「悲願」という言葉があります。「念願」も時を経ると悲願になります。身命をなげうってでもという悲壮な決意を伴ってくるからです。そうなってこそ、人の願いは本物になるという考え方です。人生の真の積極性というものは、浅い楽観主義からでなく、反対にかなしみ(愛・悲・哀)を底辺に置いた、しっかりした悲観・諦観から生じてくるものなのではないでしょうか。
愛と慈悲との違いを知る
「辛気臭いことばかり並べるな」「愛は喜びなんだから、大いに賛美して楽しめばいいじゃないか」――と言うなかれ。子供から大人になるということの意味を噛み締めてほしいのです。愛は、ただ発散すればいいものなのでしょうか?
キリスト教の説く「愛」と、仏教の説く「慈悲」とのニュアンスの相違もそのあたりにあります。それが分かって、初めて日本人らしい人間観を身につけてきたと言えるでしょう。「愛」が「かなしい」ものだと知って、そのように日本語を使いこなせるようになる教育も、最近の日本人の忘れ物のひとつではないでしょうか。
歌かなし佐久の草笛
もっとも、「愛」を「かなしい」と読む心は、単なる悲哀を意味しているとは言えないでしょう。人間のみならず、自然もまた「いとしく」「かなしい」ものであると、古人は表現しています。
藤村の詩に「暮れゆけば浅間も見えず 歌哀し佐久の草笛」とあります。この「かなし」は、決して人間の日常的な哀しみではなく、より美的な纏綿たる情緒を指し示していることは言うまでもありません。こうした自然観の中にも、伝統的な日本人の美意識があります。
「愛」は「共生」という語と対にしてとらえるべきです。人は何かと共生して生きる以外に、健やかに生きるすべを持っていません。共生する相手は、人でもいいし物でもいいし神とか自然とかでもいいと思います。でも、全ての命の足元には「かなしみ」があってこそ「愛」が「愛」であるということを、古来の人々は知っていたのではないでしょうか。