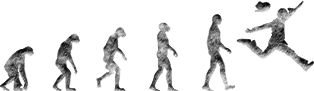「ふるさと」と民俗学の絆を理解し、そこを発射台にしよう

ふるさとは遠い。空間的なことでなく、時間的な意味ではるか遠くにあるのが「ふるさと」です。ウブな昔の自分には、地球を逆回転させても、もう二度と戻れません。「ふるさと」の存在する次元は、時間軸の上なのです。ならば、「ふるさと」を思うことは無意味なのかと言うと、決してそうではありません。
ふるさとには一切があった
「ふるさと」には何があったでしょうか。改めて自分の記憶に問えば、家族と自然との他には何もなかった、という答に行き着くことでしょう。しかし、さらにもう一歩じっくりと考え直してみれば、それ以外この世に何が必要なのだろうか、という疑問が湧いてきます。つまり、「ふるさと」には何もなかったけれども、一切があったとも言えます。
アリは生きていることが「ふるさと」
会社とか、仕事とか、地位とか、名誉とか、資産とか、学歴とか……人間的な能力を発揮するための、種々の装置も人生には大切なものでありましょう。
しかし自分を一匹のアリンコだと想定してしまうと、そんなものは全てどうでもいいことに見えてきます。本能だけで生きているアリンコにとっては、生きているというそのことが、そのまま「ふるさと」です。それが一切です。
理想を失っていく人間たち
人生哲学からは「真・善・美」が人間の理想だとされますが、真実が欺瞞に塗り替えられ、善美が悪と醜とに染め抜かれていくこと、それが人間の「生きる」という営みの実際であったとしたら……?
人間は「ふるさと」を汚し、否定し、葬ることによって、アリンコから人になっていくのではないでしょうか。観念をもてあそび、言葉を複雑に操作し、聖なるものを卑俗なものへとおとしめて、人類の繁栄を勝ち得ているのかもしれません。
「ふるさと」と民俗学
でも待ってください、人間には自分では意識できない自己というものがあるのです。意識は自己の全てではなくて、一部なのです。その見えない部分がカルマであり、DNAであり、フロイトの言う無意識の世界なのです。
民俗学の目的は、自分という小世界の拠って立つ足場を、民俗の形に探ることです。つまり、民族の魂を儀式や民話の中に探り、個人には見えない民族のDNAを民俗風土の中に発見しようとするものです。それは一つの自己発見の旅であり、「ふるさと」というものはその周辺に存在する何ものかだと言えましょう。
因果を引きずって生きている
今の自分が引きずっているものは、必ずしも自己の行為の結果だけではありません。自分の生まれるはるか以前からの、先祖たちからの因果をも延々と引きずって生きています。
あるいは日本国民としての歴史の罪障も、両肩にずっしりと負わされていると言えます。正の遺産を受け継ぐ代わりに、負の遺産をも避けがたく押し付けられて生きているのです。
母が語ってくれた「もう一つの世界」
思えば幼少期の私たちは、ほとんど無文字の世界の住民でした。まだ文字というものを知らぬままに、それにもかかわらず膨大なものごとを次々に感じ、覚え、吸収していきました。この時代に、子供の豊かな想像力を支えていたものは、母親の話し方であり、対応でした。かつては昔話や伝説を、きりもなく寝物語に語ってくれたものです。
理知や判断力の乏しい幼少期には、誰もが未知なるものの只中に放り出されていました。母の語る肉声の説話は、無文字のまま、子供に広い未知の「もう一つの世界」を与えてくれました。思えば、母の背中で見た故郷の赤い夕焼けは、「もう一つの世界」への入り口でした。
民族の想いと願いを知ること
「ふるさと」とは、母の教えてくれた「もう一つの世界」の総称だと考えてみたいのです。民話とか神話とかには、それを語り継いだ民族の想い、願いが色濃く宿っているものです。柳田國男が「遠野物語」で掘り下げてくれた民俗学の核心は、それだと言えましょう。
幼児にとっては、母そのものが「ふるさと」です。昔、母が優しく語ってくれた「もう一つの世界」、それは確実に子供の感性の根に沁み込みました。誰もがそれにかかとを載せて、そこから人生を出発したはずです。
発射台としての「ふるさと」
「ふるさと」が単なる「過去」や「思い出」の別称であるとしたら、詰まらないものです。後ろ向きではなく、未来に向かって意味のある過去こそが、本当の「ふるさと」でしょう。
前述のように、欺瞞と醜悪に汚れまみれなのが人間であるとしても、なお人間の魂には「希望」が巣食っているものです。自分を育ててくれた民族のDNAを信じてみることが、心の中に「希望」を生成します。未来を生み出す過去、将来を生み出す動機としての過去、いわば自分を出発させる発射台としての過去が、本当の「ふるさと」であると言えます。