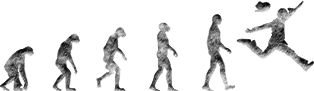変わる働き方の意味、報酬至上主義から意欲優先主義へ

1 対価を得るだけじゃダメ?
報酬によってのみ人が動くという時代は、過去のものになりつつあるという。
終身雇用が崩壊し、定期昇給と年功序列の限界が広く一般的な気分として広まり、特定企業に属し続ける働き方にも陰りが見え始めている状況で、報酬よりもやりがいや意欲的になれる場所を欲している人々が増えたというのである。
つまり自分らしくありたいとか、生きている甲斐が欲しいということである。こうした自分の意欲を中心に求める人々の出現が、労働のあり方、端的には社会構造そのものを変えようとしている。
2 リスクと引換えに
しかし、従来型の報酬至上主義を捨てて意欲優先主義に移行するということは、未だ社会が報酬至上の考えで成り立っていることを思えばリスキーである。やりがいを求めて生活が維持できる見通しがあるならばよいが、そういう人ばかりではないだろう。
それでも多くの人が自らのエンジンを稼働させるための動機を“カネ”に求めず、自分らしさややりがいに重きを置き、生き方について新しい定義を求めようとしている。このことについては、もう少し当事者性を持って考えてみる必要があるのではないかと思う。
3 組織の論理の中で
今あなたはどこかの組織に属し、与えられた業務と責任の中で日々労働に勤しんでいるだろうか。だとすれば、少なからず葛藤やストレスや不満を抱えていることだろう。
全くノンストレスという例は少ないはずだ。それを組織のせいにする気持ちは誰もが一度は抱くものだと思う。
企業は経済活動を通じて無限に拡張を目指すという性質を有している。そういう生態のイキモノだと思っていい。顧客サービスの向上や労働者への福利厚生は手段に過ぎず目的ではない。
あくまで目的は拡張にあって、経済的発展を抜きに企業は成立しない。そのことは紛れも無い。
当然だが、組織が大きくなればなるほど個人は歯車化し、主観的不満は封じ込められる。その中で自己実現などという個人の論理は存立しにくい。
会社の体制や体質、雰囲気や業務のありかたに疑問を抱きつつも、結局は組織活動を優先し、己の気持ちを抑えねばならない。そのスタンスに徹することを組織も従業員に求めるだろう。
制約を避けリスクも避けながら(つまり人生の偶有性を避けながら)生きてきた世代は、そうした組織の論理に馴染めず、早々に退職する例が多いのだろう。企業の側でもそのつなぎとめには四苦八苦している。
4 組織に属していてはダメ?
夢や理想を追うのならそういう組織からは抜け出して・・・。その考えを否定はしない。いっぽうで生きてゆくためには組織に残るほうが賢明だ。という考えも否定しない。しかし、選択肢はそれだけではないということに我々はうすうす感づき始めている。
何も退職してフリーになることだけが新時代を生き抜くすべではない。悲壮感に彩られた組織の奴隷で居続けるという道だけでもない。むしろ、組織内にあっても自己実現を可能とする方法を模索することは現実的に可能であると思う。
組織内での苦しみは、属する組織の基準内だけで自分の人生の満足度を高めようとするという矛盾から生じるものだと私は思っている。
5 概念の違いを乗り越える
現状はちょうど古いOS(報酬至上主義)が新OS(意欲優先主義)との互換性を失う瞬間に似ている。
規格が合わないとか概念の違いなど理由は幾つもあろうけど、とにかく新しい概念をメインマシンたる古い筐体(ここでは組織のこと)にインストールすることができないという状態である。これを乗り越えるにはどうすればいいか。
従来型の報酬至上主義を適用した組織にある限りは、それに従うつもりで動き(つまり旧OSをとりあえずは走らせ)、しかし一方で自分の中に仮想的に意欲優先主義(新OS)を運用してみるのである。
これまではOSの適用先はひとつだと思っていたが、自分自身をメインマシンと仮定してOSそのものを自分に適用してしまう。
つまり旧OS上に仮想化したOSをもう一つ走らせている状況を想像してみればいい。それは言うほどたやすくはないが不可能ではない。
このOSの仮想化がもたらす効果は何か。私の考えはこうだ。
自らの人生上の優先順位を意識して目標を設定、さらに行動指針を樹立し、持続的に自己管理してゆくという新しいベクトルを従来の組織論理の上に並走させるということ。これを可能にする心の組み換えだ。
具体的には・・・
主軸が現在の職にあるなら、まずは職は人生の一部であって主軸ではないということを認識する。
主軸はあくまで自分の人生(20年30年という先にまで連なる自分の人生の本道であり、組織の目指す路線ではない)に置く。職が自分を支配しているのではなく、職を利用した現在の自分があるという主導権の再確認だ。
そうした認識で生活をしていると、やがて古いOSはある段階をもって役割を終える。それまでは利用できる側面を保持しつつ、時機を待つというスタンスは決して後ろ向きでも消極的でもないのである。