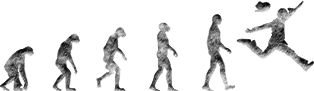楽しんで自分を点検する記録術!毎日続ける1日1ページの効用

日記の新しい概念
みなさんは日記をつけているでしょうか。今風の言い回しにするとライフログというところですか。
でもライフログはいわゆる従来の日記とはやや趣きが異なりますね。ライフログは、たとえば睡眠時間や食べたもの、いった場所など、ありとあらゆる自身の身の回りの事象をデジタル媒体に記録してゆくことを指すことが多いようです。
しかし今回扱うのはデジタルではなく、アナログにおける記録としてより日記に近い概念で「日常体験記録」をつけてゆくことの楽しみについてです。
1日1ページの記録
糸井重里さんが主催する「ほぼ日刊イトイ新聞」で毎年発売している「ほぼ日手帳」は、毎日の記録を1日1ページの手帳にアナログで記録してゆくというコンセプトで人気を博し、アナログ式ライフログのブームを作りました。
この1日1ページというのは、そこに込められる情報量が実に絶妙です。例えば購入したもののレシートを貼って添え書きをつけておく、単純にタスクを書きつけておく、睡眠時間や食べたもの、いった場所など、絵や写真を添えて記録してゆくこともできます。
何だ、そんなものどんなノートや手帳を使っても同じじゃないかとお思いの方もいらっしゃるかもしれません。そうです。別にどこのメーカーのどの製品じゃないといけないということはありません。自分の好みの様式、サイズのものを選べばいいと思います。
重要なのは日々途切れることなく365日分のページがあって、それぞれにきっちり日付が入っているというところなのです。ですからそもそもノートや手帳の体裁である必要すらないのかもしれません。
日付とともにある体験の記憶
日付が入っているということは、その日に何をしたのか何が起きたのかをさかのぼり安いというメリットがあります。書く内容はなんでもいい。毎日書かねばならないとか、コレを書かねばならないとか、そんな制約は不要。
好きなペンで、好きな方法で記録をつけていい。そしてそれが一冊完結した時、自分が1年を通してどういう変化をし続けてきたのかということを、ニヤニヤしたりしかめっ面をしながら眺めて見ることをおすすめします。
このさかのぼり体験の有無が生き方を考える上で、きっと重要な要素になってくると思います。
日々を漫然と過ごしているとあっという間に自分の体験は過去の彼方です。私たちは自分で思う以上に自分の身の回りのことに対して無頓着です。
一昨日の朝食のメニューを思い出すことも、何時に入眠したのかも、どれくらいWEBに接続していたのかも、単に記憶の中から思い出すのは容易ではありません。それが1ヶ月前、1年前ならなおのことです。
そんな瑣末なことはわざわざ思い出す必要はないのかもしれません。
しかし、人の記憶というのは例えば臭いや味や色あいや手触りなどと共にあるように、無意識に五感と連動しており、それはほとんどが日常の些細な事と結びついています。その記録があるとき重要な意味を帯びてくるということはあると思うのです。
過去と未来の橋渡し
日付の順に自分の体験記録をする。この作業で自分データを蓄積するのは、なれないと苦痛かもしれません。私も最初はそうでした。意義は感じていても継続するのはなかなか大変です。
私の場合は自分の人生の転機に「もっと日々の記録をつけておけばよかった」と落胆したところからスタートし、続けるうちに自分の履歴が溜まってゆくことへの喜びが付帯するようになりました。
自分が何を経験し、それにどんな感想を抱いたか、何を見、何をし、何を失い、得たか。それらの点を線で結ぶとき、自分のアイデンティティが確認できるように思えるのです。
まさに、それは自分像を浮かび上がらせ具現化する仕組みであるといえるのではないかと思います。
1日1ページは、自分像具現化へのアプローチのためのひとつの解答だと思っています。自分にはどんな記録が必要か、自分が欲しているのは何であるかを求める。
これは結局自らを観察し得手不得手を知り、何が不足しているかを見極めてゆく事でしかわかりません。そのきっかけに日々を綴る1日1ページが最適であると思うのです。
描いているときは日々無心で、別にそれに意味を問うたり意義をもたせようとする必要はないのかもしれません。どんなに雑でも書かない日があってもいい。でもほそぼそでも続けていることに意味があります。
いつの間にか自分の形式が出来上がり、無理なく普通に書けるようになれば習慣化は成功したと言えます。
1日1ページの追求は最終的に自分の「様式」を発見するところで完成形となります。それは日々の変化の中で少しずつ形を変えてゆきつつも、自分らしさとして確かに結実します。
誰かの作った「様式」に自分を合わせていたのではおそらく生涯自分らしくは成り得ないのでしょう。だから下手であろうが雑であろうが自分の「様式」を発見してそれを貫きます。
それが過去と未来を橋渡す基盤となるはずです。